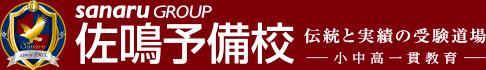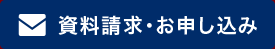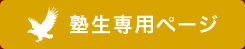愛知県公立高校入試 問題・解答・分析(2026年度)
国語
ワンポイント分析
文章全体から内容を正しく理解し、論理構造を捉える読解力が求められる入試問題
例年通り、現代文の大問が二題出題されました。そのうち大問一の論説文は8点、大問三の小説文は7点という配点になりました。
論説文では、脱文挿入の問題や、論の進め方の特徴を捉える問題、生徒の感想を並び替える問題など、一貫して論の筋道を適切に理解して解答する力が求められました。
小説文では、登場人物の心情の変化を読み取る力が重要でした。直接的な心情表現だけでなく、行動や会話、状況描写から心情を推測する必要がありました。
全体として、文章の一部分だけを手掛かりに解答するのではなく、文章全体の構造や登場人物の心情の流れを的確に捉える読解力が求められる入試問題でした。日頃から選択肢と本文を丁寧に照合する学習を積み重ねることが重要です。
例年通り、現代文の大問が二題出題されました。そのうち大問一の論説文は8点、大問三の小説文は7点という配点になりました。
論説文では、脱文挿入の問題や、論の進め方の特徴を捉える問題、生徒の感想を並び替える問題など、一貫して論の筋道を適切に理解して解答する力が求められました。
小説文では、登場人物の心情の変化を読み取る力が重要でした。直接的な心情表現だけでなく、行動や会話、状況描写から心情を推測する必要がありました。
全体として、文章の一部分だけを手掛かりに解答するのではなく、文章全体の構造や登場人物の心情の流れを的確に捉える読解力が求められる入試問題でした。日頃から選択肢と本文を丁寧に照合する学習を積み重ねることが重要です。
Pick up!
大問一(五)
一昨年から新たに出題された配点が3点の問題は、今年度、大問一(五)で出題されました。一昨年は生徒6人の意見を並び替える問題でしたが、今年度は本文を読んだ1人の生徒が書いた感想が6つに分けられ、筋道が通るように並び替えて、2番目、4番目、6番目を答える問題で、配点は2番目が正解で1点、4番目、6番目が正解で2点、合計3点というものでした。文の流れを丁寧に追いながら指示語にも注目をして並び替える力が求められました。
一昨年から新たに出題された配点が3点の問題は、今年度、大問一(五)で出題されました。一昨年は生徒6人の意見を並び替える問題でしたが、今年度は本文を読んだ1人の生徒が書いた感想が6つに分けられ、筋道が通るように並び替えて、2番目、4番目、6番目を答える問題で、配点は2番目が正解で1点、4番目、6番目が正解で2点、合計3点というものでした。文の流れを丁寧に追いながら指示語にも注目をして並び替える力が求められました。
数学
ワンポイント分析
計算・関数・図形の多領域にわたる思考を柔軟に使いこなす総合的数学力が必要
今年度の数学入試は昨年度同様、2点問題3問・1点問題16問の全19問構成でした。大問1は計算や関数、データの活用など基礎的な内容が中心で、確実に得点したい問題が並びました。大問2では確率や関数の利用が問われ、特に(2)は関数と図形の性質を融合して解答を導く力が必要でした。大問3は角度・平面図形・空間図形が出題され、(2)②では三平方の定理の活用、(3)②は空間図形において相似を活用することが鍵となる難問でした。全体として難度は昨年度並みで、基礎問題を素早く処理し、図形の応用問題に時間を確保できたかが高得点の分かれ目となりました。
今年度の数学入試は昨年度同様、2点問題3問・1点問題16問の全19問構成でした。大問1は計算や関数、データの活用など基礎的な内容が中心で、確実に得点したい問題が並びました。大問2では確率や関数の利用が問われ、特に(2)は関数と図形の性質を融合して解答を導く力が必要でした。大問3は角度・平面図形・空間図形が出題され、(2)②では三平方の定理の活用、(3)②は空間図形において相似を活用することが鍵となる難問でした。全体として難度は昨年度並みで、基礎問題を素早く処理し、図形の応用問題に時間を確保できたかが高得点の分かれ目となりました。
Pick up!
大問3(2)②
BEをxとする。
∠BAF=∠AFD(平行線の錯角)
△ABEを点Aを中心に反時計回りに90°回転するとBとDが重なり、三角形ADE´ができる。
∠E´AF=∠E´FAより2角が等しいので、△E´AFはE´A=E´Fの二等辺三角形と言える。
E´F=E´D+DFよりx+9と表せるので、E´Aも同様にx+9と表せることから
三平方の定理より、
xの2乗+12の2乗=(x+9)の2乗【E´Dの2乗+ADの2乗=E´Aの2乗】
x=7/2
四角形AECF=正方形ABCD-△ABE-△AFDより
四角形AECF=144-21-54
四角形AECF=69㎠
BEをxとする。
∠BAF=∠AFD(平行線の錯角)
△ABEを点Aを中心に反時計回りに90°回転するとBとDが重なり、三角形ADE´ができる。
∠E´AF=∠E´FAより2角が等しいので、△E´AFはE´A=E´Fの二等辺三角形と言える。
E´F=E´D+DFよりx+9と表せるので、E´Aも同様にx+9と表せることから
三平方の定理より、
xの2乗+12の2乗=(x+9)の2乗【E´Dの2乗+ADの2乗=E´Aの2乗】
x=7/2
四角形AECF=正方形ABCD-△ABE-△AFDより
四角形AECF=144-21-54
四角形AECF=69㎠
社会
ワンポイント分析
資料を読み取り、知識と結びつける力が問われる入試問題
昨年度の構成を踏襲し、歴史・地理・公民の各分野から大問が2題ずつ、各分野小問7問ずつ出題されているバランスの取れた形式となっています。最大の特徴は、単なる一問一答の暗記した知識の確認ではなく、「探究活動」や「発表」をベースとした出題形式にあります。生徒の作成したレポートや発表メモという設定のもと、写真、歴史資料、統計データ、地図など多様な資料が提示されています。受験生は、これら複数の資料を正確に読み取り、持っている知識と結びつけて論理的に解答を導き出す力が求められます。歴史では日本と世界の出来事の関連付け、地理では自然環境と産業の考察、公民では多様な働き方や税・防災といった現代社会の課題への理解が問われています。
複数の条件をすべて満たして得点となる設問も多くあり、日ごろから図や表、統計データなどの資料に触れ、「なぜそうなるのか」という背景と知識を結びつけて深く理解する学習が不可欠です。
昨年度の構成を踏襲し、歴史・地理・公民の各分野から大問が2題ずつ、各分野小問7問ずつ出題されているバランスの取れた形式となっています。最大の特徴は、単なる一問一答の暗記した知識の確認ではなく、「探究活動」や「発表」をベースとした出題形式にあります。生徒の作成したレポートや発表メモという設定のもと、写真、歴史資料、統計データ、地図など多様な資料が提示されています。受験生は、これら複数の資料を正確に読み取り、持っている知識と結びつけて論理的に解答を導き出す力が求められます。歴史では日本と世界の出来事の関連付け、地理では自然環境と産業の考察、公民では多様な働き方や税・防災といった現代社会の課題への理解が問われています。
複数の条件をすべて満たして得点となる設問も多くあり、日ごろから図や表、統計データなどの資料に触れ、「なぜそうなるのか」という背景と知識を結びつけて深く理解する学習が不可欠です。
Pick up!
大問2(1)
3つの古文書の現代語訳の資料から読み取れる、4つの内容の正誤を判定する問題です。4つ全て正解して1点となる完全解答形式のため、高い集中力が求められます。攻略の鍵は、歴史の暗記知識ではなく、与えられた資料から客観的に正誤を判断する情報処理能力です。例えば、Ⅰの資料には改元の理由が「すい星の出現」と明記されており(Cは正)、天皇の死による改元の記述はありません(Bは誤)。また、Ⅱの資料で内裏の火事が記録されていますが、Ⅲの資料からその後も元号が変わっていないことが読み取れるため、火事による改元(D)も誤りです。
現代の「天皇代替わりで改元」という先入観を捨て、資料の事実のみに忠実に向き合えるかが試される良問です。
3つの古文書の現代語訳の資料から読み取れる、4つの内容の正誤を判定する問題です。4つ全て正解して1点となる完全解答形式のため、高い集中力が求められます。攻略の鍵は、歴史の暗記知識ではなく、与えられた資料から客観的に正誤を判断する情報処理能力です。例えば、Ⅰの資料には改元の理由が「すい星の出現」と明記されており(Cは正)、天皇の死による改元の記述はありません(Bは誤)。また、Ⅱの資料で内裏の火事が記録されていますが、Ⅲの資料からその後も元号が変わっていないことが読み取れるため、火事による改元(D)も誤りです。
現代の「天皇代替わりで改元」という先入観を捨て、資料の事実のみに忠実に向き合えるかが試される良問です。
理科
ワンポイント分析
実験をベースとした幅広い知識の習得と、原理原則の根本理解が不可欠
例年通り、各分野からバランスよく出題され、問題数は20問で2点問題は2問でした。極端に難度の高い問題は無かったものの、受験生が誤答を選んでしまいやすい問題がいくつか見られました。今年度は、全般的にデータの読み取り問題が多かったことが特徴で、特に大問3では「中和」と「電気分解」についての正しい理解が必要でした。実験条件を落ち着いて読み取り、表にまとめられたデータを使って考え、解く力が求められました。小問では、各分野で、根本原理の理解を前提とした、考えさせる出題が多く見られました。
例年通り、各分野からバランスよく出題され、問題数は20問で2点問題は2問でした。極端に難度の高い問題は無かったものの、受験生が誤答を選んでしまいやすい問題がいくつか見られました。今年度は、全般的にデータの読み取り問題が多かったことが特徴で、特に大問3では「中和」と「電気分解」についての正しい理解が必要でした。実験条件を落ち着いて読み取り、表にまとめられたデータを使って考え、解く力が求められました。小問では、各分野で、根本原理の理解を前提とした、考えさせる出題が多く見られました。
Pick up!
大問3(4)
表3をもとにすると、電流の大きさを1.50Aとして40分間電流を流したとき、加える水酸化ナトリウム水溶液の体積が35.0㎤とわかります。この条件と比較して、電流の大きさが4/3倍の2.00A、流す時間が3/4倍の30分となれば、加える水酸化ナトリウム水溶液の体積は変わらず、35.0㎤となり、正解は「ウ」となります。
表3をもとにすると、電流の大きさを1.50Aとして40分間電流を流したとき、加える水酸化ナトリウム水溶液の体積が35.0㎤とわかります。この条件と比較して、電流の大きさが4/3倍の2.00A、流す時間が3/4倍の30分となれば、加える水酸化ナトリウム水溶液の体積は変わらず、35.0㎤となり、正解は「ウ」となります。
英語
ワンポイント分析
語彙力・資料を読みとる力・文脈を把握する力が問われる入試
総じて、英単語の語彙力が問われる入試問題でした。今年度の入試問題で使用された英単語には、初めて見た単語もあったかもしれません。たとえば、provide、ritual、I’d ratherなど、教科書ではあまり見慣れない英単語が使われました。また、資料を読み取る力も必要で、何を示す図なのか、英語力とは別の情報処理能力も問われる入試でした。
総じて、英単語の語彙力が問われる入試問題でした。今年度の入試問題で使用された英単語には、初めて見た単語もあったかもしれません。たとえば、provide、ritual、I’d ratherなど、教科書ではあまり見慣れない英単語が使われました。また、資料を読み取る力も必要で、何を示す図なのか、英語力とは別の情報処理能力も問われる入試でした。
Pick up!
大問2(2)
(2)下線部③にあてはまるように、次のアからキまでの中から六つ選んで正しく並べ替えるとき、2番目、4番目、6番目にくるものをそれぞれ選びなさい。
ア cold イ lost ウ when エ is オ decrease カ outside キ it
整序問題を解くためには2つの力が必要です。1つ目は英文の意味を読み取る読解力、2つ目は文法的に正しく語を並べる文法力です。
まず下線部③のひとつ前の文にある「... they are used a lot in hot weather.(暑い天気によく使われる)」に注目します。この文脈から、③には「外が寒いときは(あまり)失くされ(ない)」という意味の文が入ると予想できます。
次に語群を確認します。decrease「減る」は不要語と判断します。残りの6語から、接続詞whenを使った副詞節(when it is cold outside)の構造を意識すると、lost when it is cold outsideという語順が導けます。意味と文法の両面からしっかり考えて解く必要がありました。
解答 2番目:ウ(when) 4番目:エ(is) 6番目:カ(outside)
解答となる文:They are not often lost when it is cold outside.
(それらは外が寒いときには、失くされることはあまりありません。)
(2)下線部③にあてはまるように、次のアからキまでの中から六つ選んで正しく並べ替えるとき、2番目、4番目、6番目にくるものをそれぞれ選びなさい。
ア cold イ lost ウ when エ is オ decrease カ outside キ it
整序問題を解くためには2つの力が必要です。1つ目は英文の意味を読み取る読解力、2つ目は文法的に正しく語を並べる文法力です。
まず下線部③のひとつ前の文にある「... they are used a lot in hot weather.(暑い天気によく使われる)」に注目します。この文脈から、③には「外が寒いときは(あまり)失くされ(ない)」という意味の文が入ると予想できます。
次に語群を確認します。decrease「減る」は不要語と判断します。残りの6語から、接続詞whenを使った副詞節(when it is cold outside)の構造を意識すると、lost when it is cold outsideという語順が導けます。意味と文法の両面からしっかり考えて解く必要がありました。
解答 2番目:ウ(when) 4番目:エ(is) 6番目:カ(outside)
解答となる文:They are not often lost when it is cold outside.
(それらは外が寒いときには、失くされることはあまりありません。)
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。