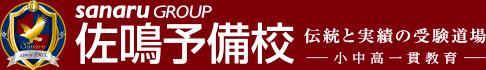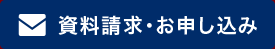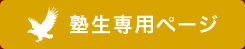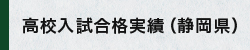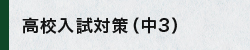静岡県公立高校入試 問題・解答・分析(2025年度)
国語
ワンポイント分析
読解力・表現力・知識の三つをバランスよく鍛えること
例年通りの出題形式で、「文学的文章」「説明的文章」「原稿の推敲」「古文」「作文」の大問五題構成でした。知識に関する問題や表現に関する問題を含むバランスのよい出題でした。大問一と大問二、大問四で、文章から読み取った内容を記述する問題が二問ずつ出題されており、これらの問題の成否が得点差につながったと思われます。問いの文の条件をしっかりと整理し、どのような解答を求められているかを考えて解答を作成する必要があり、受験生にとっては苦労する問題でした。
例年通りの出題形式で、「文学的文章」「説明的文章」「原稿の推敲」「古文」「作文」の大問五題構成でした。知識に関する問題や表現に関する問題を含むバランスのよい出題でした。大問一と大問二、大問四で、文章から読み取った内容を記述する問題が二問ずつ出題されており、これらの問題の成否が得点差につながったと思われます。問いの文の条件をしっかりと整理し、どのような解答を求められているかを考えて解答を作成する必要があり、受験生にとっては苦労する問題でした。
Pick up!
大問一 問六
本文中で「梛」が刀匠になるという夢について考えていることを、「梛」の心境を推測していることが分かる比喩を用いた表現を含めてまとめる記述問題でした。最後の一文に「心の中は台風みたいに大荒れかもしれないけれど」とあり、この比喩表現で、「ぼく」が推測している「梛」の心の内が表されています。また、「梛」の「あきらめなければなれるんじゃないかなって……。」という台詞から、夢に向かって諦めずに進もうとする「梛」の考えを読み取ることができました。静岡県公立高校入試では、複数の解答条件を設定し、本文中から適切な内容を探させる問題が毎年出題されています。今年度も、正しく条件を読み取り、必要な内容を拾い出した上で、指定字数内にまとめる、複合的な力が高得点のカギといえます。
本文中で「梛」が刀匠になるという夢について考えていることを、「梛」の心境を推測していることが分かる比喩を用いた表現を含めてまとめる記述問題でした。最後の一文に「心の中は台風みたいに大荒れかもしれないけれど」とあり、この比喩表現で、「ぼく」が推測している「梛」の心の内が表されています。また、「梛」の「あきらめなければなれるんじゃないかなって……。」という台詞から、夢に向かって諦めずに進もうとする「梛」の考えを読み取ることができました。静岡県公立高校入試では、複数の解答条件を設定し、本文中から適切な内容を探させる問題が毎年出題されています。今年度も、正しく条件を読み取り、必要な内容を拾い出した上で、指定字数内にまとめる、複合的な力が高得点のカギといえます。
数学
ワンポイント分析
設問ごとの難度の差が際立った入試
今年の静岡県公立高校入試の数学は、「空間図形」「関数」「円の証明」において難度の高い問題が出題されました。よって、全体的には、例年より難度が高くなったと言えるでしょう。出題順や問題量、形式などは昨年度のものと大きく変更はありませんでした。「データの活用」において、ヒストグラムと箱ひげ図を合わせて分析していく問題が出題され、戸惑った生徒もいたかもしれません。また、大問4の「空間図形」に時間を取られすぎてしまうと、焦りから他の問題の正答率が下がってしまいます。入試の中盤にある問題でもあるため、問題をとばしてほかの問題に移ることも必要だったでしょう。
一方で、難度の高かった上記の単元以外は標準的な問題で構成されていたため、得点すべき問題を見極めて優先的に問題を解いていく事が求められた入試でした。
今年の静岡県公立高校入試の数学は、「空間図形」「関数」「円の証明」において難度の高い問題が出題されました。よって、全体的には、例年より難度が高くなったと言えるでしょう。出題順や問題量、形式などは昨年度のものと大きく変更はありませんでした。「データの活用」において、ヒストグラムと箱ひげ図を合わせて分析していく問題が出題され、戸惑った生徒もいたかもしれません。また、大問4の「空間図形」に時間を取られすぎてしまうと、焦りから他の問題の正答率が下がってしまいます。入試の中盤にある問題でもあるため、問題をとばしてほかの問題に移ることも必要だったでしょう。
一方で、難度の高かった上記の単元以外は標準的な問題で構成されていたため、得点すべき問題を見極めて優先的に問題を解いていく事が求められた入試でした。
Pick up!
大問7(1) 円の証明
平行線が絡んだ証明でした。2組の角が等しいことを説明するために、まずは、平行線の同位角と円周角を用いて、∠AEF=∠ACB=∠BPGを示します。
次に、△CADと△BAGが頂角が等しい二等辺三角形であることから、∠BAG=∠CADであることを示します。それぞれの角度から∠CAPを除いた∠FAE=∠PADを示し、最後に円周角を用いて∠FAE=∠GBPであることに繋げて、相似を証明しましょう。
大問7(2) 弧の長さ
半径がわかっているため、中心角が必要です。∠DOPが示されていないため、円周角である∠DBPを求めていきます。平行線の錯角から∠EBC=68°とわかり、弧DCの円周角と、△CADの内角の和を用いれば∠ACD=44°とわかります。弧ADの円周角と、弧APに対する円周角90°を用いて、∠DBP=46°であることを求め、弧の長さに繋げましょう。
平行線が絡んだ証明でした。2組の角が等しいことを説明するために、まずは、平行線の同位角と円周角を用いて、∠AEF=∠ACB=∠BPGを示します。
次に、△CADと△BAGが頂角が等しい二等辺三角形であることから、∠BAG=∠CADであることを示します。それぞれの角度から∠CAPを除いた∠FAE=∠PADを示し、最後に円周角を用いて∠FAE=∠GBPであることに繋げて、相似を証明しましょう。
大問7(2) 弧の長さ
半径がわかっているため、中心角が必要です。∠DOPが示されていないため、円周角である∠DBPを求めていきます。平行線の錯角から∠EBC=68°とわかり、弧DCの円周角と、△CADの内角の和を用いれば∠ACD=44°とわかります。弧ADの円周角と、弧APに対する円周角90°を用いて、∠DBP=46°であることを求め、弧の長さに繋げましょう。
英語
ワンポイント分析
英作文・長文読解のボリュームアップ
「リスニング」「対話文読解」「英作文」「長文読解」の4題からなる大問構成や配点は、昨年度と同様でした。ただし、長文の分量は昨年度に比べて30語ほど増え、英文を読み慣れていない生徒にはやや難しく感じられたかもしれません。
大問2(6)の自由英作文においても、指定語数が15語以上と増えています(昨年度は12語以上、一昨年度は7語以上)。また、長文読解では、日本語での記述問題において、答えとなる英文の構造を正確にとらえる力に加え、語彙力も求められ、少し難しく感じた受験生もいたでしょう。
近年、大学入試や高校入試の英語においては、読解する長文自体の分量が増加する傾向にあり、その攻略には、文法事項の整理に加え、語彙力を高め、解答力を養うトレーニングが不可欠です。英単語・熟語や文法の基礎を早い段階で固めた上で、和文英訳や長文読解などの実戦練習を十分に積み重ねていくことが、入試本番での成功につながります。
「リスニング」「対話文読解」「英作文」「長文読解」の4題からなる大問構成や配点は、昨年度と同様でした。ただし、長文の分量は昨年度に比べて30語ほど増え、英文を読み慣れていない生徒にはやや難しく感じられたかもしれません。
大問2(6)の自由英作文においても、指定語数が15語以上と増えています(昨年度は12語以上、一昨年度は7語以上)。また、長文読解では、日本語での記述問題において、答えとなる英文の構造を正確にとらえる力に加え、語彙力も求められ、少し難しく感じた受験生もいたでしょう。
近年、大学入試や高校入試の英語においては、読解する長文自体の分量が増加する傾向にあり、その攻略には、文法事項の整理に加え、語彙力を高め、解答力を養うトレーニングが不可欠です。英単語・熟語や文法の基礎を早い段階で固めた上で、和文英訳や長文読解などの実戦練習を十分に積み重ねていくことが、入試本番での成功につながります。
Pick up!
大問3
「君は野球のやり方を教えてくれた。」と「僕たちと野球をやりに静岡に戻ってきてくれたらなあ。」という日本語を英訳する問題でした。
「野球のやり方」は「疑問詞+to+動詞の原形」を使い、how to play baseballと表しましょう。「教える」はshowやteachを使うのが適切ですが、過去形で表現することに注意しましょう。
また、「戻ってきてくれたらなあ」という表現からI wishを使った仮定法で書くことが望ましいでしょう。「~に戻ってくる」の英語表現come back to ~も書き慣れていない生徒がいたかもしれません。
解答例
You taught me how to play baseball.
I wish you would come back to Shizuoka to play baseball with us.
「君は野球のやり方を教えてくれた。」と「僕たちと野球をやりに静岡に戻ってきてくれたらなあ。」という日本語を英訳する問題でした。
「野球のやり方」は「疑問詞+to+動詞の原形」を使い、how to play baseballと表しましょう。「教える」はshowやteachを使うのが適切ですが、過去形で表現することに注意しましょう。
また、「戻ってきてくれたらなあ」という表現からI wishを使った仮定法で書くことが望ましいでしょう。「~に戻ってくる」の英語表現come back to ~も書き慣れていない生徒がいたかもしれません。
解答例
You taught me how to play baseball.
I wish you would come back to Shizuoka to play baseball with us.
社会
ワンポイント分析
社会的事象の深い理解に加え、思考力と表現力が求められる問題
大問1が歴史、大問2が日本地理、大問3が世界地理、大問4が公民を中心とした出題という形式は例年通りでした。約50%が記号選択問題、約50%が語句記述、短文記述、長文論述の問題です。全体として、社会的事象に対する関心と理解が求められる問題でした。
語句記述の問題は標準的な出題が多く、問題演習により知識の定着が確実にできているかが問われました。24もの地図、グラフ、図、表、資料が用いられ、資料を正確に読み取り解答につなげる力が要求されました。また、資料を正確に読み取る力に加え、その内容を使い思考することで解答にたどり着く問題も出題されました。例年通り、長文論述の問題が出題され、複数のグラフから考えられる内容を考察し70字程度にまとめる文章表現力も要求されました。
大問1が歴史、大問2が日本地理、大問3が世界地理、大問4が公民を中心とした出題という形式は例年通りでした。約50%が記号選択問題、約50%が語句記述、短文記述、長文論述の問題です。全体として、社会的事象に対する関心と理解が求められる問題でした。
語句記述の問題は標準的な出題が多く、問題演習により知識の定着が確実にできているかが問われました。24もの地図、グラフ、図、表、資料が用いられ、資料を正確に読み取り解答につなげる力が要求されました。また、資料を正確に読み取る力に加え、その内容を使い思考することで解答にたどり着く問題も出題されました。例年通り、長文論述の問題が出題され、複数のグラフから考えられる内容を考察し70字程度にまとめる文章表現力も要求されました。
Pick up!
大問3(4)b
2023年のパナマ運河で船舶の1日当たりの通行許可数を制限しなければならなくなった理由を記述する問題
資料3からパナマ運河では「船舶が通行するたびに、運河の途中にある湖の水を大量に使用する」ことを読み取ります。図4からはパナマ運河がある地域と「少雨傾向がみられる領域」が重なっていることがわかります。この2点を関連付けて船舶の通行に使用する湖の水が減っていることを記述することが、出来るか否かが成否を分けます。
大問4(3)b
日本の水道事業の現状と、その現状から考えられる日本の水道事業の問題点を、70字程度で記述する問題
グラフ5から「法定耐用年数を超えた水道管」の割合が増加していることと、「更新された水道管」の割合が減少していることを読み取ります。グラフ6から「日本の水道事業にたずさわる職員数」が減少していること、グラフ7からは「日本の水道事業の料金収入」が減少していることを読み取ります。グラフから読み取った日本の水道事業の現状を踏まえて、日本の水道事業の維持が困難になるという問題点を適切に記述できることがポイントです。
2023年のパナマ運河で船舶の1日当たりの通行許可数を制限しなければならなくなった理由を記述する問題
資料3からパナマ運河では「船舶が通行するたびに、運河の途中にある湖の水を大量に使用する」ことを読み取ります。図4からはパナマ運河がある地域と「少雨傾向がみられる領域」が重なっていることがわかります。この2点を関連付けて船舶の通行に使用する湖の水が減っていることを記述することが、出来るか否かが成否を分けます。
大問4(3)b
日本の水道事業の現状と、その現状から考えられる日本の水道事業の問題点を、70字程度で記述する問題
グラフ5から「法定耐用年数を超えた水道管」の割合が増加していることと、「更新された水道管」の割合が減少していることを読み取ります。グラフ6から「日本の水道事業にたずさわる職員数」が減少していること、グラフ7からは「日本の水道事業の料金収入」が減少していることを読み取ります。グラフから読み取った日本の水道事業の現状を踏まえて、日本の水道事業の維持が困難になるという問題点を適切に記述できることがポイントです。
理科
ワンポイント分析
用語の暗記よりも、記述力や計算力が点差につながる問題
例年大問が6問出題され、本年度も例外なく6問でした。大問1の小問集合に加え、物理・化学・地学・生物の分野で各1問ずつ、さらに地学をもう1問出題した形の、計6問です。用語などの知識を問う問題はもちろんですが、各分野において実験や観察の実例に対して、それに基づく記述問題や計算問題が多く出題されました。全問総数に対して、約半数が計算問題や記述問題、作図の問題となっていて、深い理解と高い表現力が必要となる問題でした。大問4(2)②の問題は、記号選択式の問題となっていますが、観測地点の太陽の南中高度と地軸の傾きを文字式としたときの、観測地点の緯度を数式で求めるという問題です。教科書などで覚えてきた知識から、もう1段階思考することを求められるような問題が散見される難度の高い出題でした。
例年大問が6問出題され、本年度も例外なく6問でした。大問1の小問集合に加え、物理・化学・地学・生物の分野で各1問ずつ、さらに地学をもう1問出題した形の、計6問です。用語などの知識を問う問題はもちろんですが、各分野において実験や観察の実例に対して、それに基づく記述問題や計算問題が多く出題されました。全問総数に対して、約半数が計算問題や記述問題、作図の問題となっていて、深い理解と高い表現力が必要となる問題でした。大問4(2)②の問題は、記号選択式の問題となっていますが、観測地点の太陽の南中高度と地軸の傾きを文字式としたときの、観測地点の緯度を数式で求めるという問題です。教科書などで覚えてきた知識から、もう1段階思考することを求められるような問題が散見される難度の高い出題でした。
Pick up!
大問4(2)②
観測地点の地軸を太陽側に傾けたとき(夏至)の太陽の南中高度は、次のように求められます。
太陽の南中高度=90°-(緯度-地軸の傾き)
この式の太陽の南中高度をa、地軸の傾きをbと置き換えると、a=90°-(緯度-b)より、緯度=90°-a+b、よって答えは「ア」です。
観測地点の地軸を太陽側に傾けたとき(夏至)の太陽の南中高度は、次のように求められます。
太陽の南中高度=90°-(緯度-地軸の傾き)
この式の太陽の南中高度をa、地軸の傾きをbと置き換えると、a=90°-(緯度-b)より、緯度=90°-a+b、よって答えは「ア」です。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。